【必見】サラリーマンができる基本的な節税【年間20万円】
※アフィリエイト広告を利用しています(更新日:2023年8月20日)
![]()

このような疑問について紹介いたします。
✔︎ 本日の内容
- 節税の基本:収入・控除・所得について
- サラリーマンにもできる節税とは
- サラリーマンができる5の節税
✔︎ 本記事の信頼性:僕のこと
私は、現在下記のテーマについて情報発信しております。

コロナの影響により、厳しい経済、給料の減収など、将来の見通しも厳しくなってきました。
そのような中、サラリーマンができる節税の基本中のキホンについて、ご紹介いたします。
節税の基本:収入・控除・所得について


サラリーマンが節税するための知識です。
●最低限の知識
- 収入=控除+所得
- 収入:会社員の額面の給料
- 控除:差し引く金額。配偶者控除、所得控除など。
- 所得:税金の対象となる金額
つまりは、
- 収入を増やす
- 控除を増やす
- 所得が少なくなる
- 税金が少なくなる
簡単に考えると、こんな感じ。
また、不動産投資をしているサラリーマンは個人事業主となっていたりします。
個人事業主となっているサラリーマンは、収入も増えておりますが、経費も多く計上されます。
そのため、このような方程式となります。
● 個人事業主サラリーマンの場合
- 収入=経費+控除+所得
- 収入が増える
- 経費が増える
- 控除が増える
- 所得が少なくなる
- 税金が少なくなる
サラリーマンにもできる節税

サラリーマンでも、税金が少なるなる様々な控除を受けることができます。
先程の紹介しましたが、
- 収入は一定
- 控除は増える
- 所得は減る
- 税金が減る
ということです。
サラリーマンでも可能な控除には、以下のようなものがあります。
● サラリーマンでも可能な控除
- 社会保険料控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 医療費控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
この中でも社会保険料控除は月収という「収入」がベースとなっております。
そのため社会保険料を抑えるためには、収入を抑制する必要があるので、大幅に抑制することは難しいです。
社会保険料は、毎月4月から6月の月収の平均で算出されます。
そのため、この時期は残業代ゼロを心掛ければ社会保険料の抑制につながるわけです。
① 個人型確定拠出年金 iDeCo

iDeCoとは個人型確定拠出年金、つまり、老後のための私的年金です。
年金には、① ベースの公的年金 ② 2階建の企業年金 ③ 自分で備える私的年金 になります。

● iDeCoのメリット
- 運用益が非課税
- 受取時も控除
- 掛金も全額所得控除
実際の節税金額の目安は、
- 会社員か自営業者か
- 勤務先に企業年金があるか
- 専業主婦か
によって変動します。
● ケースごとに掛金の上限額がある
| 自営業 | 会社員(企業年金ない) | 公務員・会社員(企業年金あり) | 専業主婦 | |
| 年間掛金限度額 | 81万6000円 | 27万6000円 | 14万4000円 | 27万6000円 |
サラリーマンであれば、月額掛金12,000円〜23,000円
専業主婦であれば、月額23,000円
ってイメージです。
● 節税の目安
| 所得税+住民税率 | 公務員・会社員(企業年金あり) | 会社員(企業年金なし)専業主婦 | |
| 330万円超 695万円以下 | 30% | 43,200円 | 82,800円 |
| 695万円超 900万円以下 | 33% | 47,520円 | 91,080円 |
| 900万円超 1800万円以下 | 43% | 61,920円 | 118,680円 |
会社員はもちろんのこと、専業主婦にとっても節税対策になります。
● iDecoのデメリット:原則60歳まで引き出せない
iDecoの1番のデメリットは、原則60歳まで引き出すことができないことです。
通常の積立投資は途中解約ができますが、iDeCoはできません。
強制的な積立になります。
② ふるさと納税
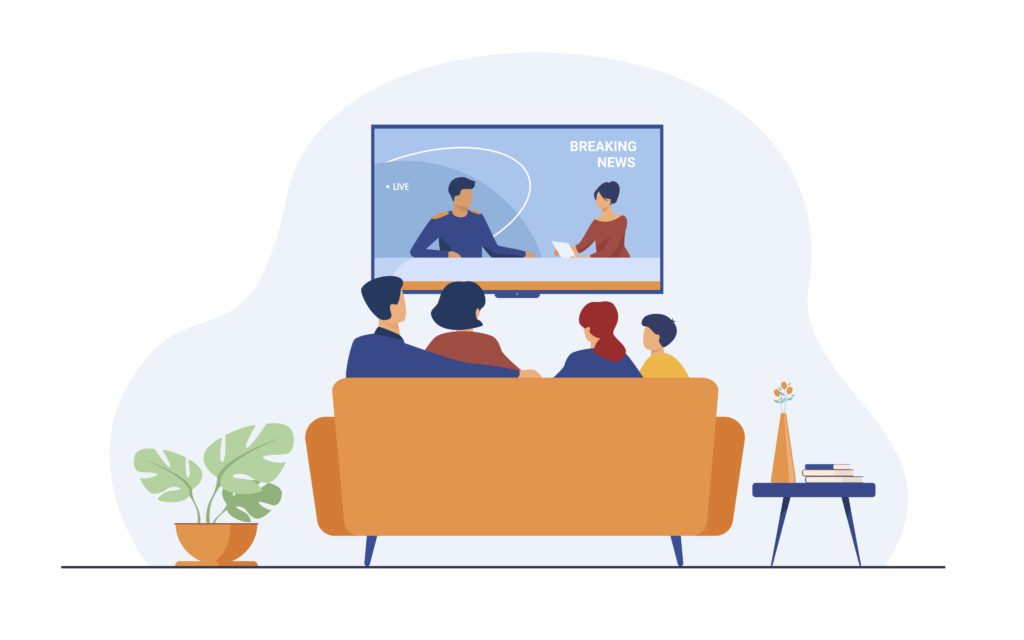
サラリーマンの基本的な節税といえば「ふるさと納税」

ふるさと納税は、2000円で「寄付した金額の税金の控除」を受けることができます。
ただし、上限があるので注意です。
● ふるさと納税のステップ
- 控除上限額をシミュレーション(源泉徴収の用意)
- 寄付サイトから返礼品の申し込み
- お礼品と証明書の到着
- ワンストップ特例申請を自治体に郵送
● ふるさと納税の注意点
- 控除上限額を超えないこと:超えたら自己負担
- 自治体6カ所以上は、確定申告が必要
ふるさと納税の初心者にとっては、寄付する自治体を5カ所以内にすることをお勧めします。
なぜなら、確定申告の手続きが不要になるからです。
ワンストップ特例申請によって、確定申告が不要になります。
● お勧めポータルサイト
- ふるなび:「わずか3分でふるさと納税はこちら!」
- さとふる: ふるさと納税!さとふるが簡単!
- ふるさとニッポン:ふるさとニッポンはこちら
個人的には、「ふるなび」と「さとふる」を使い倒しております。
③ 生命保険料控除
生命保険料控除は、負担した保険料分だけ税金が安くなります。
年末調整にて支払った保険料が節税できるのです。
● 生命保険料控除
- 一般保険料控除:最高4万円(定期保険、終身保険、学資保険など)
- 個人年金保険料控除:最高4万円(個人年金保険など)
- 介護医療保険料控除:最高4万円(医療保険、がん保険、介護保険など)
●年間の払込保険料と控除額
| 年間の払込保険料 | 控除額 |
| 2万円以下 | 保険料の全額 |
| 2万円〜4万円 | (保険料×1/2)+1万円 |
| 4万円〜8万円 | (保険料×1/4)+2万円 |
| 8万円超 | 4万円 |
④ 医療費控除

医療費も節税に利用できるケースがあります。
医療費控除の金額=「支払い合計ー支給保険金−10万円」
● 医療費控除の対象例
- 医科歯科の診療費
- 処方医薬品代
- 入院費
- ドラッグストアの医薬品
- 通院の交通費
- 松葉杖などの購入費
医療費控除の対象は、このように幅広くいのです。
だからこそ、領収書・レシートをきちんと保存しておきましょう。
⑤ 住宅ローン減税

家を買った人が対象の減税です。
● 住宅ローン減税の対象
- 新築住宅
- 中古住宅
- リフォーム
最高500万円にも及ぶ、ローン残高の1%分税金が安くなります。
● 住宅ローン減税の控除額
- 一般住宅:年末残高(4000万円まで)×控除率1%:控除期間10年間
- 長期優良住宅:年末残高(5000万円まで)×控除率1%:控除期間10年間
控除期間は10年間ですが、消費増税後は13年間と延長しております。
まとめ


本日は「サラリーマンでもできる節税は?」について紹介いたしました。
以下の3点についてご紹介しました。
- 節税の基本:収入・控除・所得について
- サラリーマンにもできる節税とは
- サラリーマンができる5の節税
できることをコツコツやることが、後々大きな節税となるでしょう。

